「カロリーを減らしても痩せない」「リバウンドを繰り返してしまう」そんな悩みを抱えていませんか?
実はその原因、ダイエット中のタンパク質量が不足しているのかもしれません。
カロリー制限だけに頼ったダイエットは、筋肉まで落としてしまい、基礎代謝を下げるリスクがあります。
結果として、痩せづらく、太りやすい体質に逆戻りしてしまうのです。
ですが安心してください。
体重1kgあたり1.4〜2.0gのタンパク質量をしっかり摂ることで、筋肉を守りながら健康的にダイエットができます。
本記事では、ダイエット中のタンパク質量や年齢別の摂取目安、効果的な食べ方、実践しやすいレシピまで、具体的に解説していきます。
正しい知識と工夫で、無理なく理想の体を目指しましょう。
Contents
ダイエット目的で1日に必要なタンパク質量
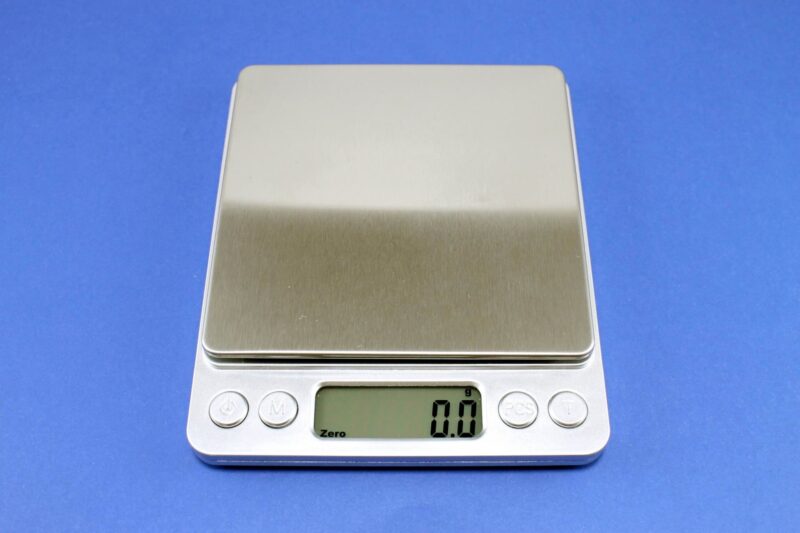
ダイエットを成功させるには、摂取カロリーをおさえるだけでなく、タンパク質の量にも気を配ることが重要です。
とくに、筋肉が減ると基礎代謝も落ちてしまい、リバウンドしやすい体質になるリスクが高まります。
ここでは、ダイエット中に意識したい適切なタンパク質量の目安や、体重に応じた摂取量を詳しく解説していきます。
ダイエット中のタンパク質量は体重✖️1.4〜2.0gが理想
ダイエット中に体重1kgあたり1.4〜2.0gのタンパク質を摂取することで、筋肉を維持できるとされています(※1)。
カロリー制限をすると、体は足りないエネルギーを筋肉を分解することで補おうとします。
これをカタボリックといい、筋肉が減ってしまう現象を指します。
結果、基礎代謝が低下し、痩せづらく太りやすい体になってしまうのです。
タンパク質を十分に摂ることで、筋肉の分解を防ぎ、基礎代謝を維持できます。
ダイエットと並行してトレーニングもしている人は、筋肉の回復と成長のために体重1kgあたり2.0gに近い量を目指すと良いでしょう。
年齢ごとのタンパク質推奨量
厚生労働省が推奨している、年齢ごとのタンパク質摂取量は以下のとおりです(※2)。
| 年齢層 | 性別 | 推定平均必要量 (g/日) |
推奨量 (g/日) |
目標量 (%エネルギー) |
|---|---|---|---|---|
| 18〜29歳 | 男性 | 50 | 65 | 13〜20% |
| 女性 | 40 | 50 | 13〜20% | |
| 30〜49歳 | 男性 | 50 | 65 | 13〜20% |
| 女性 | 40 | 50 | 13〜20% | |
| 50〜64歳 | 男性 | 50 | 65 | 13〜20% |
| 女性 | 40 | 50 | 13〜20% | |
| 65〜74歳 | 男性 | 50 | 65 | 13〜20% |
| 女性 | 40 | 50 | 15〜20% | |
| 75歳以上 | 男性 | 50 | 60 | 15〜20% |
| 女性 | 40 | 50 | 15〜20% |
タンパク質摂取基準は、年齢と性別で細かく定められています。
「推定平均必要量」と「推奨量」に加え、「目標量」という指標もあります。
目標量は1日の総カロリーに対するたんぱく質の割合を示したものです。
高齢者は筋肉維持のためか、やや高めの設定となっています。
妊娠・授乳中の女性は通常より多く必要になるケースもあるため、不安な場合はかかりつけの医師や産婦人科での相談をおすすめします。
ダイエット中にタンパク質量を増やす3つのメリット

ダイエット中にタンパク質量を増やすメリットは以下の3つです。
- ダイエットの効率を高める
- 満腹感が続きやすい
- 筋力維持につながる
ダイエットの成果を高めるには、必要なタンパク質量を意識して増やすことが重要です。
メリットを理解して、効果的なダイエットを始めましょう。
メリット1. ダイエットの効率を高める
タンパク質を増やすことで、ダイエットの効率が高まります。
その秘密は「食事誘発性熱産生(DIT)」という体の仕組みにあるのです。
DITとは、食べ物を消化・吸収・代謝する際に消費されるエネルギーのことを指します。
タンパク質は摂取カロリーの約20〜30%をDITで消費するため、実質的な摂取カロリーをおさえられます。
炭水化物や脂質のDITが5〜10%程度なのと比べると、その差は歴然です。
さらに、タンパク質は血糖値の上昇を緩やかにする働きもあるため、インスリンの過剰分泌を防ぎます。
インスリンは脂肪を蓄積させるホルモンなので、この分泌おさえられることで脂肪がつきづらくなります。
毎食20g以上のタンパク質を摂ることで、1日中代謝が高い状態をキープできるでしょう。
メリット2. 満腹感が続きやすい
タンパク質は、ほかの栄養素に比べて高い満腹効果があり、空腹感をおさえるのに役立ちます。
タンパク質を摂取すると、満腹中枢に働きかけるホルモンの分泌が活発になるのです。
とくに「ペプチドYY」や「GLP-1」といったホルモンが増えることで、長時間満腹感が持続します。
これらは腸から分泌されるホルモンで、脳に「もう十分食べた」という信号を送る役割があります。
ダイエット中の空腹感は挫折の大きな原因になりますが、タンパク質をしっかり摂ることでこの問題を解決しやすくなるでしょう。
メリット3. 筋力維持につながる
ダイエット中のタンパク質摂取は、カタボリックを防ぐためにも大切です。
体重1kgあたり1.4〜2.0gのタンパク質を摂取することで、筋肉の分解を防ぎやすく、筋力を維持できます(※1)。
とくにダイエット中は、筋トレも並行することで、筋肉量を維持しやすくなりメリハリのある理想的な体型を実現できます。
ダイエット中のタンパク質効果を引き出す3つのテクニック

ダイエット中のタンパク質効果を引き出すテクニックは以下の3つです。
- 3〜4時間おきに摂取する
- サプリメントも併用する
- 寝る直前にカゼインプロテインを摂取する
ダイエット中にタンパク質量を意識して摂取しているのに、思うような結果が出ないと悩んでいませんか。
実は、タンパク質は摂り方次第で効果が大きく変わってくるのです。
ここでは、プロのトレーナーも実践している3つのテクニックを紹介していきます。
これらのテクニックを組み合わせることで、理想の体型へと近づきやすくなります。
テクニック1.3〜4時間おきに摂取する
タンパク質を3〜4時間おきに摂取することで、筋肉の分解を防ぎながらダイエットを進められます(※1)。
体内では常に筋肉の合成と分解が繰り返されており、バランスを合成側に傾けることが重要です。
一度に大量のタンパク質を摂っても、体が吸収できる量には限界があります。
1回の食事で吸収できるタンパク質は約20〜30gといわれており、それ以上は無駄になってしまう可能性があるのです。
朝食で20g、間食で10g、昼食で25g、間食で10g、夕食で25gというように分散させることで、コンスタントに栄養を供給でき、腸内環境の維持にもつながります。
とくに起床後と運動後は筋肉がタンパク質を必要としているタイミングなので、優先的に摂取しましょう。
このリズムを習慣化することで、空腹感もおさえられ、タンパク質量を安定して確保できるため、ダイエットが続けやすくなるはずです。
テクニック2.サプリメントも併用する
ダイエット中に必要なタンパク質量を満たすのが難しい場合は、サプリメントの併用がおすすめです。
なかでも、プロテインパウダー(以下、プロテイン)は手軽に良質なタンパク質を摂取できる優れたサプリメントです。
とくに、ホエイプロテインは吸収が早く、運動後の摂取におすすめ。
ホエイプロテインとは、牛乳から作られる乳清タンパク質のことで、必須アミノ酸をバランスよく含んでいます。
1回あたり20〜30gのプロテインを水や牛乳で溶かして飲むことで、ダイエットに必要なタンパク質量を簡単に補給できます。
ホエイプロテインは優れたタンパク質源ですが、乳糖不耐症の人はお腹を下す可能性があるため注意が必要です。
乳糖不耐症の人は、大豆を原料とした「ソイプロテイン」など、別のサプリメントを候補に入れましょう。
また、サプリメントはあくまで補助的な役割なので、基本は食事からの摂取を心がけることが大切です。
テクニック3.寝る直前にカゼインプロテインを摂取する
就寝前のカゼインプロテインの摂取は、睡眠中の筋肉分解を防ぐうえで効果的です。
吸収速度がゆっくりなため、長時間にわたり体内へ栄養を届けられます。
寝る30分〜1時間前に20〜30gのカゼインプロテインを摂取することで、睡眠中も筋肉に栄養が行き渡ります。
こうした細かな工夫が、ダイエット中の筋肉維持には欠かせません。
ダイエット中のタンパク質摂取でおさえておきたい3つの注意点

ダイエット中のタンパク質摂取でおさえておきたい注意点は以下の3つです。
- こまめなタンパク質摂取は胃への負担が大きくなる
- 高カロリーな調理法(揚げ物・油炒め)だと逆効果になる
- 加工肉(ソーセージ・ハム)ばかりに頼ると脂質や塩分過多になる
良かれと思って実践していることが、実は体に負担をかけていたり、ダイエットの妨げになっていたりするケースは少なくありません。
正しくタンパク質を摂取するためにも、注意点を一緒に見ていきましょう。
注意点1.こまめなタンパク質摂取は胃への負担が大きくなる
こまめにタンパク質を摂取することは大切ですが、胃腸への負担も考慮する必要があります。
タンパク質は早ければ4時間ほどで消化されるため、頻繁に摂取すると胃が休まる時間がなくなってしまうのです(※3)。
消化不良を起こすと、栄養の吸収率が下がるだけでなく、胃もたれや膨満感の原因にもなります。
対策として、植物性タンパク質と動物性タンパク質をバランスよく組み合わせることが重要です。
豆腐や納豆などの大豆製品は比較的消化しやすいため、間食には植物性タンパク質を選ぶと良いでしょう。
また、よく噛んで食べることや、消化酵素を含む食品を一緒に摂ることで、胃腸の負担を軽減できます。
注意点2.高カロリーな調理法(揚げ物・油炒め)だと逆効果になる
タンパク質食品を揚げ物や油炒めなど高カロリーな調理法で摂取すると、ダイエット効果が薄れてしまいます。
たとえば、鶏もも肉(皮なし)100gは約128kcalですが、唐揚げにすると約249kcaになってしまいます(※4)。
ダイエット中は茹でる、蒸す、焼く(少量の油で)などの調理法を選ぶことが重要です。
グリルやオーブンを使えば、余分な脂を落としながら調理できます。
調味料も高カロリーなものは避け、ハーブやスパイス、レモン汁などで味付けすると良いでしょう。
タンパク質の効果を最大限に活かすためには、調理法にも気を配ることが大切です。
注意点3.加工肉(ソーセージ・ハム)ばかりに頼ると脂質や塩分過多になる
手軽だからといって加工肉ばかりに頼るのは、ダイエットにも健康にも良くありません。
ソーセージやハム、ベーコンなどの加工肉には、想像以上に脂質と塩分が含まれているのです。
たとえばソーセージ100gには約30gの脂質が含まれており、ほかの栄養素も合わせると約319kcalも摂取することになります(※4)。
さらに、加工肉には保存料や発色剤などの添加物も多く含まれています。
塩分の過剰摂取は、むくみの原因となり、体重が減りにくくなる要因にもなるのです。
ダイエット中は、適切なタンパク質量を意識しながら、新鮮な肉や魚、卵、大豆製品を中心に選びましょう。
どうしても加工肉を使う場合は、週に1〜2回程度におさえ、野菜と組み合わせて食べることで栄養バランスを整えることが大切です。
ダイエットに必要なタンパク質量が摂取できるレシピ3選

毎日同じメニューでは飽きてしまい、ダイエットが続かなくなることもありますよね。
ダイエットに必要なタンパク質量を意識しながら、カロリーをおさえた料理を作ることで、楽しみながら無理なくダイエットを進められます。
これから紹介する3つのレシピは、1食あたり20g以上のタンパク質が摂取できるうえ、作り置きも可能で、忙しい日々にもぴったりです。
美味しく食べながら、必要なタンパク質量をきちんと摂取して理想の体型を目指せる、実践的なダイエットレシピをご紹介します。
1. 鶏むね肉とブロッコリーのガーリック炒め
鶏むね肉とブロッコリーのガーリック炒めは、ダイエット中に必要なタンパク質量を確保しつつ、ビタミンやミネラルも摂れる優秀なレシピです。
【作り方】
- 鶏むね肉(皮なし)150gを一口大に切り、料理酒と塩コショウで下味をつける
- ブロッコリー100gを小房に分け、電子レンジで2分ほど加熱しておく
- フライパンにオリーブオイル小さじ1を熱し、みじん切りニンニク1片を香りが出るまで炒める
- 鶏むね肉を入れ、中火で3分ほど炒める
- 火が通ったらブロッコリーを加え、軽く炒め合わせる
- 仕上げに醤油小さじ2を回しかけて完成
ポイントは、鶏むね肉を炒めすぎないことです。
パサつきを防ぐために、下味の料理酒が重要な役割を果たします。
1食あたり250kcal未満とは思えない満足感があり、しっかり食べたい日にもおすすめです。
2. 豆腐とツナのヘルシーサラダ
豆腐とツナのヘルシーサラダは、タンパク質約25gを手軽に摂取できる簡単レシピで、カルシウムや食物繊維も補えます。
【作り方】
- 木綿豆腐150gを水切りし、食べやすい大きさにカットする
※水切りはキッチンペーパーで包み、電子レンジで1分加熱すると簡単 - ツナ缶(水煮)1缶の水気を軽く切る
- レタス・きゅうり・トマトなどお好みの野菜と一緒にボウルへ入れる
- ポン酢大さじ2とごま油小さじ1を混ぜたドレッシングを作る
- 全体を軽く和えて完成
このサラダの良いところは、火を使わずに作れることと、ダイエットに欠かせないタンパク質量を植物性と動物性の両方からバランスよく補えることです。
さっぱりしていて食べやすく、200kcal程度と低カロリーなので夜遅い食事にも向いています。
カロリーは約200kcalと低めなので、夜遅くなったときの食事にも適しています。
3. 鮭ときのこのホイル焼き
鮭ときのこのホイル焼きは、タンパク質約30gに加えて良質な脂質も摂れる理想的なレシピです。
【作り方】
- 生鮭1切れ(120g)に塩コショウを軽く振る
- アルミホイルの上に鮭を置き、しめじ・えのきなどのきのこ類100gと薄切り玉ねぎ50gをのせる
- 料理酒大さじ1とバター5gを加える
- アルミホイルでしっかり包む
- フライパンに水を1cm程度入れ、包んだホイルを置いて蓋をし、中火で12分ほど蒸し焼きにする
- 仕上げにレモン汁をかけて完成
鮭に含まれるオメガ3脂肪酸は、脂肪燃焼を助ける働きがあり、ダイエット中にも最適。
オメガ3脂肪酸とは、体内で合成できない「必須脂肪酸」の一種です。
約280kcalとカロリーも控えめで、必要なタンパク質量も摂れるため、ダイエット中でも満足できる一品として活用したいメニューです。
ダイエット中におすすめ|タンパク質が多い食材一覧表

| 食品 | カロリー (kcal) | タンパク質量 (g) |
|---|---|---|
| 鶏むね肉(皮なし) | 113 | 24.4 |
| 鶏ささみ | 121 | 29.6 |
| 卵(全卵) | 134 | 12.5 |
| 木綿豆腐 | 73 | 7.0 |
| 納豆 | 184 | 16.5 |
| ツナ缶(水煮) | 139 | 18.4 |
| 鮭 | 175 | 28.1 |
| まぐろ | 115 | 26.4 |
| 低脂肪牛乳 | 42 | 3.8 |
鶏肉や魚は高タンパクかつ低カロリーで、筋肉を維持しながら体脂肪を減らしたい人に向いています。
大豆製品は植物性タンパク質を補えるため、動物性と組み合わせるとさらに効果的です。
目的に合わせて食品を選ぶことで、効率よく体づくりを進められます。
ダイエットを成功させるタンパク質量を知り食生活に取り入れよう

ダイエット中のタンパク質摂取は、単なる「栄養補給」にとどまらず、筋肉維持・代謝維持という2つの役割を担う重要なポイントです。
タンパク質を、体重1kgあたり1.4〜2.0g摂取することで、筋肉を維持しながら健康的なダイエットができます。
加えて、3〜4時間おきの摂取やカゼイン・ホエイなど目的に合ったサプリの使い分け、カロリーを抑えた調理法も取り入れることで、より高い効果が得られます。
鮭や鶏むね肉、豆腐など身近な食材を使ったレシピを活用すれば、毎日の食事が楽しみになり、継続のモチベーションにもつながるはずです。
正しい知識と実践があれば、ダイエットはもっと前向きに、そして確かな成果へとつながっていきます。
内容の正確性を保つため、以下の信頼できる情報源をもとに記事を作成しています。