短期間で痩せるダイエット法は数多くありますが、結局のところ基本を無視して成功した人はいません。
体重を減らすためには、摂取カロリーよりも消費カロリーを上回るという原則があり、これはどんな方法にも共通する真理です。
また、栄養バランスの取れた食事と運動の継続こそが、健康的に痩せるためのカギになります。
この記事では、ダイエットの基本を「食事・運動・継続」の3軸でわかりやすく解説しているので参考にしてください。
Contents
ダイエットに役立つ5つの基本知識
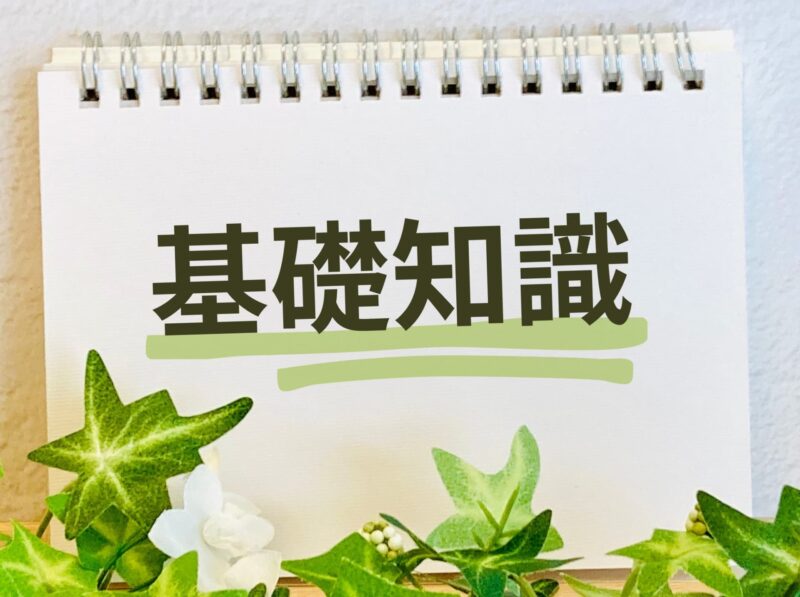
ダイエットに役立つ基本知識は以下の5つです。
- 消費カロリー>摂取カロリーで痩せる
- 食事管理と運動を並行して痩せる
- 運動だけでは痩せられない
- 継続することが大切
- ダイエットが必要かどうかはBMIで判断する
ダイエットの基本を理解することは、健康的に痩せるための第一歩です。
まずは基本を押さえて、自分に合ったダイエット方法を見つけていきましょう。
ダイエットの基本1.消費カロリー>摂取カロリーで痩せる
体重を減らすには、消費カロリーが摂取カロリーを上回る必要があります。
これはダイエットの基本中の基本です。
1日の摂取カロリーが消費カロリーを下回ると、体は不足分を補うために蓄積された脂肪をエネルギーとして使います。
たとえば、1日2000kcal消費する人が1800kcalしか摂取しなければ、理論上200kcal分の脂肪が燃焼されるということです。
ただし、極端なカロリー制限は体調を崩す原因になります。
基礎代謝を下回らないよう摂取カロリーを調整しましょう。
ダイエットの基本2.食事管理と運動を並行して痩せる
ダイエットを成功させるには、食事管理と運動の両方が欠かせません。
食事だけを制限すると、筋肉量が減って基礎代謝が下がってしまいます。
理想的なのは、バランスの良い食事で栄養を摂りながら、適度な運動で筋肉を維持することです。
週に2〜3回の筋トレと、軽い有酸素運動を組み合わせると効果的でしょう。
食事は極端に減らすのではなく、タンパク質を中心に栄養バランスを整えることがポイントです。
ダイエットの基本3.運動だけでは痩せられない
運動だけで痩せようとする人は多いですが、実はこれだけでは難しいのが現実です。
30分のジョギングで消費できるカロリーは約200〜300kcal程度で、おにぎり1個分とほぼ同じです。
運動で消費したカロリー以上に食べてしまえば、体重は減りません。
さらに、運動後は食欲が増すことも多く、つい食べ過ぎてしまうケースもあります。
ダイエットの基本は、筆者の体感としては食事管理が8割、運動が2割です。
極端な話、ダイエットだけが目的であれば、食事管理だけでも痩せられます。
一方で健康的な体づくりも目指すのであれば、食事管理と並行して運動習慣も求められます。
ダイエットの基本4.継続することが大切
ダイエットの基本は継続することです。
短期間で急激に痩せても、もとの生活に戻れば必ずリバウンドしてしまいます。
体には恒常性という、もとの状態を維持しようとする機能があるからです。
これは、「ホメオスタシス」とも呼ばれます。
1週間で5kg痩せるような極端な方法より、1ヶ月で1〜2kgの頻度でダイエットする方が体に優しく、続けやすいでしょう。
小さな変化を積み重ねることで、気づけば大きな成果につながります。
毎日の習慣を少しずつ改善して、無理なく続けられる自分だけのペースを見つけましょう。
ダイエットの基本5.ダイエットが必要かどうかはBMIで判断する
自分にダイエットが必要かどうかは、BMIという指標で確認できます。
BMIとは、肥満度を表す数値です。
BMIは、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で求められます。
日本人の場合、BMI18.5〜25が標準体重とされています(※1)。
BMIが25以上であれば、ダイエットの必要性が高まりますし、逆に18.5以下であれば食べる量を増やすことを検討するのが良いでしょう。
運動ダイエットの基本5選

基本の運動ダイエットは以下の5つです。
- ウォーキング
- ジョギング
- 水泳
- サイクリング
- ヨガ
運動は、健康的に痩せるための王道なダイエット法です。
ただし、いきなりハードな運動を始めると、体を痛めたり続かなかったりすることが多いもの。
まずは自分の体力レベルに合った運動から始めることが、ダイエットの基本ともいえる考え方です。
運動1.ウォーキング
ウォーキングは手軽に始められる有酸素運動のひとつです。
特別な道具も必要なく、歩きやすい靴さえあれば今すぐ始められます。
ポイントは、背筋を伸ばして大きく腕を振り、少し早歩きを意識することです。
通勤時にひと駅分歩いたり、エレベーターではなく階段を使ったりするだけでも効果があります。
膝や腰への負担が少ないため、運動初心者の人でも安心して続けられます。
毎日の習慣にすることで、基礎体力が向上し、より強度の高い運動にもチャレンジできるようになるでしょう。
運動2.ジョギング
ジョギングは、ウォーキングよりも消費カロリーが高い有酸素運動です。
始めは5分走って5分歩くなど、無理のないペースから始めましょう。
呼吸は、鼻から吸って口から吐くリズムを意識すると楽に走れます。
週に3回、20〜30分程度から始めて、徐々に時間や頻度を増やしていくのがおすすめです。
走った後のストレッチも忘れずに行うことで、疲労回復が早まり、ケガの予防にもなります。
運動3.水泳
水泳は全身を使う運動で、カロリー消費量が高いのが特徴です。
水の浮力により関節への負担が少ないため、膝や腰に不安がある人でも安心して取り組めます。
泳ぎが苦手な人は、水中ウォーキングから始めるのもよいでしょう。
水の抵抗を受けながら歩くだけでも、陸上より多くのエネルギーを消費します。
プールに通う必要があるため継続のハードルは高めですが、その分効果も期待できます。
週に2回程度から始めて、少しずつ泳ぐ距離や時間を延ばしていきましょう。
運動4.サイクリング
サイクリングは、楽しみながら続けられる有酸素運動です。
自転車があれば、通勤や買い物のついでに運動できるのも魅力です。
坂道を含むコースを選べば、より高い運動強度で脂肪燃焼効果が期待できます。
サドルの高さは、ペダルが一番下にきたときに膝が少し曲がる程度に調整しましょう。
音楽を聴きながら、景色を楽しみながらなど、自分なりの楽しみ方を見つけることが継続のコツです。
運動5.ヨガ
ヨガは、柔軟性と筋力を同時に高められる運動です。
深い呼吸とポーズを組み合わせることで、自律神経も整えられます。
自律神経とは、体温や心拍数などを自動的に調節する神経のことです。
ストレス解消やリラックス効果も期待できますよ。
基本の食事ダイエット5選

基本の食事ダイエットは以下の5つです。
- カロリー制限
- 糖質制限
- 脂質制限
- 断食
- PFCバランス
食事管理はダイエットの要となる部分で、運動以上に体重減少に直結します。
さまざまな食事法がありますが、自分の生活スタイルや体質に合った方法を選ぶことがポイントです。
ここでは、基本的な5つの食事ダイエット法について解説します。
それぞれにメリットとデメリットがあるので、特徴を理解した上で選びましょう。
食事1.カロリー制限
カロリー制限は、王道のダイエット法です。
ポイントは、基礎代謝を下回らない程度にカロリーを抑えることです。
以下の表に男女や年齢ごとの基礎代謝の平均をまとめているので参考にしてください(※2)。
男性の基礎代謝量
| 年齢 | 基準体重 (kg) | 基礎代謝量 (kcal/日) |
|---|---|---|
| 18〜29歳 | 63.0 | 1,510 |
| 30〜49歳 | 68.5 | 1,530 |
| 50〜69歳 | 65.0 | 1,400 |
| 70歳以上 | 59.7 | 1,280 |
女性の基礎代謝量
| 年齢 | 基準体重 (kg) | 基礎代謝量 (kcal/日) |
|---|---|---|
| 18〜29歳 | 50.6 | 1,120 |
| 30〜49歳 | 53.0 | 1,150 |
| 50〜69歳 | 53.6 | 1,110 |
| 70歳以上 | 49.0 | 1,010 |
アプリを使えば、簡単にカロリー計算ができるので便利です。
食事2.糖質制限
糖質制限は、ご飯やパン、麺類などの炭水化物を控える食事法です。
糖質を減らすことで血糖値の上昇を抑え、脂肪の蓄積を防ぐ効果があります。
1日の糖質摂取量を50〜130g程度に抑えるのが目安です。
糖質を減らす分、タンパク質や脂質でエネルギーを補う必要があります。
ただし、極端な糖質制限は頭がボーッとしたり、便秘になったりすることがあります。
まずは夕食の主食を半分にするなど、無理のない範囲から始めてみましょう。
食事3.脂質制限
脂質制限は、文字どおり油分の多い食事を控えて摂取カロリーを減らす方法です。
脂質は1gあたり9kcalと、糖質やタンパク質の2倍以上のカロリーがあります。
そのため、脂質を控えるだけでも自然と1日の総摂取カロリーを抑えやすくなります。
脂質制限ダイエットを成功させるには、食品選びだけでなく調理法にも工夫が必要です。
油を使わずに「蒸す」「茹でる」「焼く」などの調理法を取り入れることで、無理なく脂質の摂取量を減らせます。
食事4.断食
断食は、一定期間食事を制限することで体重を減らす方法です。
最近注目されているのは、16時間断食です。
16時間断食は、1日のうち8時間だけ食事をして、残り16時間は水分のみで過ごします。
睡眠時間も断食(16時間)に含まれるので、比較的取り組みやすいです。
さらに、断食中はオートファジーという細胞の浄化作用も活性化されます。
オートファジーとは、古くなった細胞を分解して新しく作り替える体の仕組みです。
ただし、いきなり長時間の断食は危険なので、体調不良を感じたらすぐに中止しましょう。
食事5.PFCバランス
PFCバランスは、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)の割合を整える食事法です。
バランスは、タンパク質が13%~20%、脂質が20%~30%、炭水化物が50%~65%程度が理想といわれています(※3)。
1日の摂取カロリーが2,000kcalの場合、PFCバランスはおよそタンパク質65〜100g、脂質44〜67g、炭水化物250〜325gが目安になります。
PFCバランスを整えた食事は極端な制限をせずにダイエットできるため、長期的に続けやすい方法といえるでしょう。
ダイエットにPFCバランスを取り入れて効率的に痩せたい人は、以下の記事も併せて参考にしてください。
ダイエット中に意識したい栄養バランスの基本!朝・昼・晩の食事メニューも紹介
ダイエットを継続させるための基本3選

ダイエットを継続させるための基本は以下の3つです。
- ダイエット仲間を作る
- ご褒美デーを設ける
- 食べてしまっても自分を責めない
ダイエットで一番難しいのは、継続することです。
ここでは、ダイエットを長く続けるための3つの基本的な方法を紹介します。
完璧を求めすぎず、少しずつ前進することがポイントです。
継続するための基本1.ダイエット仲間を作る
ダイエット仲間を作ることは、モチベーション維持に効果的です。
ひとりで頑張っていると、つらいときに諦めてしまいがちですが、仲間がいれば励まし合えます。
SNSでダイエットアカウントを作ったり、友人や家族と一緒に始めたりするのもよいでしょう。
お互いの進捗を報告し合うことで、適度なプレッシャーと責任感が生まれます。
また、成功体験を共有したり、失敗を笑い合ったりすることで、ダイエットが楽しくなるでしょう。
仲間の存在は、くじけそうなときの大きな支えになります。
ダイエット中のモチベーションを維持させて、痩せたい人は以下の記事も参考にしてください。
ダイエットのモチベーションを上げる方法12選!維持するコツやNG行動なども紹介
継続するための基本2.ご褒美デーを設ける
週に1回程度、好きなものを食べられる日を作ることで、普段の食事制限も頑張れるようになります。
このご褒美デーは、チートデイとも呼ばれ、代謝を活性化させる効果もあるのです。
ただし、暴飲暴食は避けて、食べたいものを適量楽しむ程度にとどめましょう。
目標を達成したときの楽しみがあることで、日々のモチベーションが保てます。
チートデイのやり方について詳しく知りたい人は、以下の記事も合わせて参考にしてください。
チートデイでダイエットの停滞期をリセット!やり方・メニュー例・注意点を解説
継続するための基本3.食べてしまっても自分を責めない
ダイエット中に食べすぎてしまっても、自分を責める必要はありません。
完璧な人間はいないので、時には失敗することもあって当然です。
大切なのは、一度の失敗で諦めずに、次の日からまた始めることです。
自分を責めすぎると、ストレスから過食につながる悪循環に陥ってしまいます。
食べてしまったら、その分を数日かけて調整すればよいだけです。
失敗を学びの機会と捉えて、なぜ食べすぎたのかを振り返ることで、次回の対策が立てられます。
ダイエットを継続させるコツを、より深く知りたい人は以下の記事も参考になります。
ダイエットを継続させるコツ10選!挫折する理由や対処法を元トレーナーが解説
ダイエットの基本を押さえれば無理せず理想の体に近づける

痩せる人と失敗する人の差は、ダイエットの基本を身につけているかどうかで決まります。
カロリー制限や運動の習慣化、そして自分に合った食事法の選択が、リバウンドを防ぎ長く続ける秘訣です。
ハードな制限ではなく、心身に負担をかけずに取り組めるペースを見つけることが大切です。
ウォーキングやヨガのように楽しめる運動を取り入れ、食べすぎた日も前向きに調整していけば、体は確実に応えてくれます。
大切なのは、数字よりも自分の体調と向き合う意識です。
ダイエットの基本を軸に、健康的で美しい体を目指していきましょう。
内容の正確性を保つため、以下の信頼できる情報源をもとに記事を作成しています。